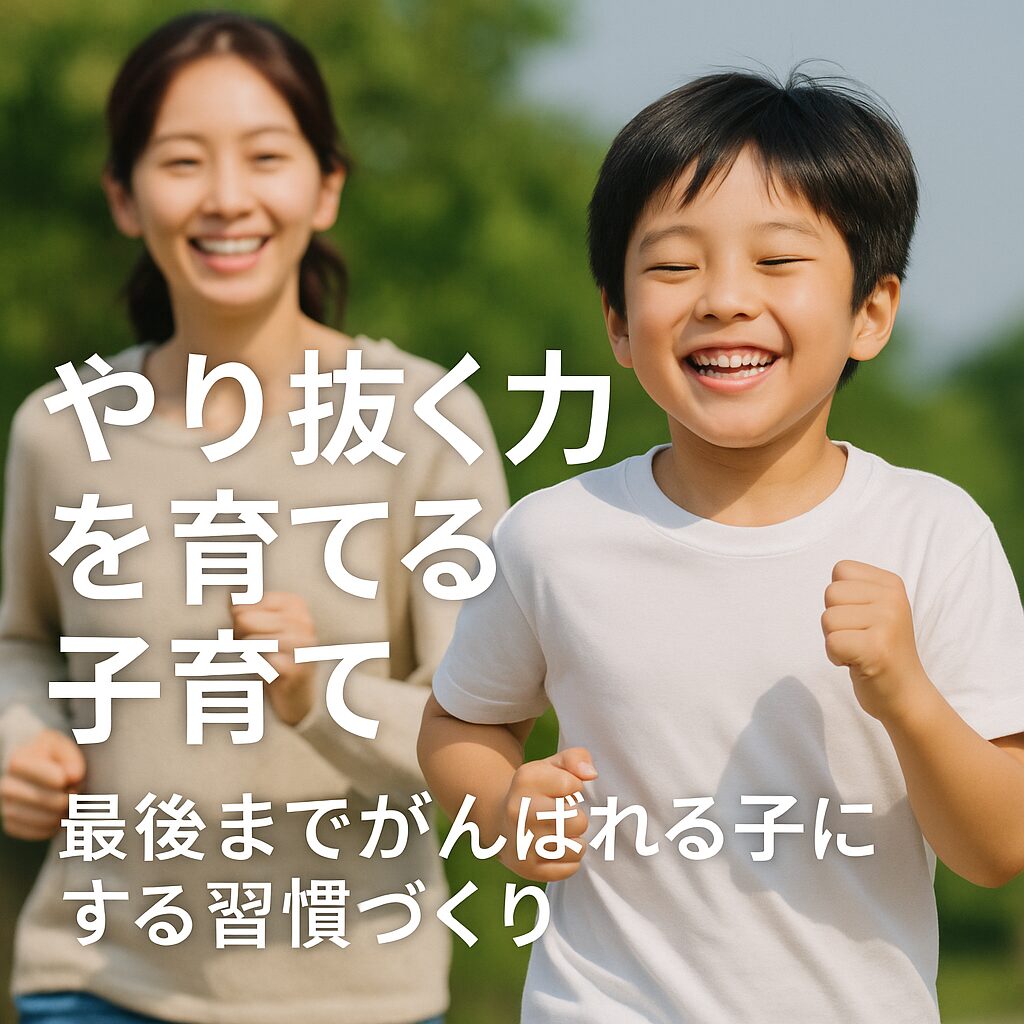最後までやりきれない…それって性格の問題?
- 宿題が途中で投げ出されている
- 習い事を始めたけど、すぐ「やめたい」
- 「どうせ無理」と言って、最初からやらない
子育てをしていると、こうした子どもの姿にモヤモヤすることはありませんか?
「うちの子、飽きっぽくて続かないんです」という相談は、よく聞かれる悩みのひとつです。
でもそれ、実は性格ではなく**「やり抜く力(グリット)」がまだ育っていないだけ**かもしれません。
「やり抜く力」とは?
心理学者アンジェラ・ダックワース氏が提唱した「グリット(Grit)」という言葉。
これは「困難に直面しても、粘り強く目標に向かって努力を続ける力」のことを指します。
IQや学力よりも、この「やり抜く力」のほうが成功や充実感に関係しているという研究結果もあるほど、注目されている能力です。
なぜ子どもは途中であきらめてしまうのか?
実は、子どもが何かを最後までやりきれない理由には、こんな背景があります。
- 成功体験が少ない:小さな達成感を積み重ねていない
- 失敗が怖い:失敗=怒られる、恥ずかしいという感覚
- 完璧主義:最初からうまくできないと落ち込んでしまう
- 親が先回りしてしまう:自分で乗り越える経験が少ない
つまり、「がんばり方」や「乗り越える経験」を知らないから、あきらめるしかなくなってしまうのです。
「やり抜く力」を育てる5つの習慣
1. 小さな成功体験を積み重ねる
いきなり大きな目標に挑戦させるのではなく、小さくて確実に達成できる目標を設定するのがコツです。
例:
- 「1ページのドリルを3日続けてみよう」
- 「朝、靴を自分でそろえるのを1週間やってみよう」
- 「ピアノの1小節だけを毎日練習」
そして達成できたら、**「やったね!」「最後までできたね!」**と、成功の喜びを一緒に味わうことが大切です。
2. 結果よりも「過程」をほめる
やり抜く力は、「できた・できなかった」の結果よりも、「どう努力したか」という過程を評価することで育ちます。
- 「最後まであきらめなかったのがすごいね」
- 「うまくいかなくても、何度も挑戦したね」
- 「悔しそうだったけど、ちゃんとやりきったね」
こうした声かけを続けると、**「がんばること=価値があること」**という意識が自然と身についていきます。
3. 失敗を「学び」に変える習慣をつける
失敗したときこそ、やり抜く力を育てるチャンスです。
- 「どうしたら次はうまくいくかな?」
- 「ここまではよくできたね。どこでつまずいたと思う?」
- 「悔しかった気持ちも大事だよ」
失敗をネガティブにとらえず、改善と再挑戦につなげる対話がポイントです。
4. 親も「最後までやる姿」を見せる
子どもは親の姿から多くを学びます。
途中で面倒になってやめたこと、イライラして投げ出したことはありませんか?
逆に、
- 「今日も早起きできた、自分にえらい!」
- 「忙しいけど、掃除最後までやってスッキリした」
- 「途中で大変だったけど、終わらせたら気持ちいいね」
こんな風に、自分の努力を言葉にして見せることで、子どもは「続けるってかっこいい」と感じるようになります。
5. 続ける意味を一緒に考える
ただ「続けなさい」「最後までやって」と言われるだけでは、やる気は育ちません。
- 「これをやりきると、どんな自分になれそう?」
- 「この練習は、何につながってると思う?」
- 「つらいとき、どう乗り越えたらいいと思う?」
こうした未来を見据えた声かけや対話が、「やり抜く」意味づけを与えてくれます。
やり抜けた経験は、一生の財産になる
子どもが何かをやりきったときの表情って、本当に誇らしげでキラキラしていますよね。
- 「自分にもできた!」
- 「がんばってよかった!」
- 「またチャレンジしてみよう!」
そんな経験が積み重なることで、やり抜く力=“折れない心”が育っていきます。
まとめ:「あきらめない力」は育てられる
やり抜く力は、もともとの性格や才能ではありません。
毎日のちょっとした声かけ、関わり方、環境のつくり方で、あとからでも育てることができる力です。
今日からできることを、ひとつだけ始めてみませんか?
- 「一緒に最後までやってみよう」
- 「途中でつまずいても、また立て直せるよ」
- 「あなたのがんばり、ちゃんと見てるよ」
そんな言葉が、子どもの未来を支える土台になります。
みなさん!!
子育てを楽しみましょう!!