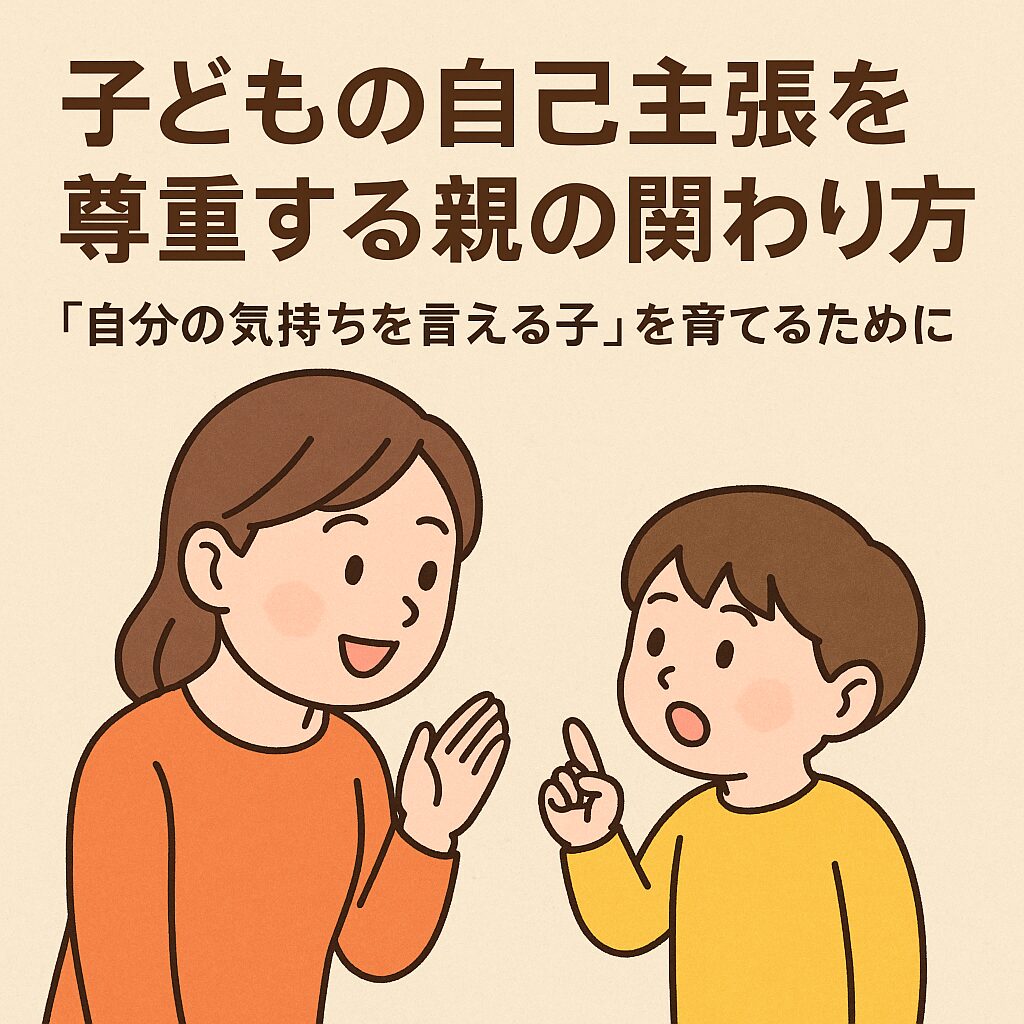〜「自分の気持ちを言える子」を育てるために〜
子どもが「こうしたい」「これは嫌だ」と自分の意思をはっきり言えることは、とても大切な力です。これを「自己主張」と呼びますが、日本の文化では自己主張が「わがまま」と受け取られることもあり、子どもが自分の気持ちを押し殺してしまうことも少なくありません。
しかし、自己主張は人との関係を築くうえで欠かせない力。大人になってからも、職場や家庭で「自分の考えを伝える力」は重要です。では、自己主張ができる子どもに育てるには、親としてどのように関わることが必要なのでしょうか?
自己主張=わがまま、ではない
まず最初に理解したいのは、「自己主張=わがまま」ではないということです。
自己主張とは、「自分の考えや気持ちを、相手の立場も考えながら伝えること」。一方、わがままは「自分の願望だけを通そうとすること」です。似ているようで、まったく違います。
たとえば、公園で遊びたくて「まだ帰りたくない!」と泣く子どもがいたとします。それは一見わがままのように見えますが、子どもなりに「まだ遊びたい」という気持ちを伝えているのです。親が「ダメ!すぐ帰るよ!」と頭ごなしに否定してしまうと、子どもは「どうせ言ってもムダ」と思ってしまい、次第に自己主張しなくなってしまいます。
子どもの気持ちを一度受け止める
子どもが何かを主張してきたとき、まずはその気持ちを「受け止める」ことが大切です。
- 「遊び足りなかったんだね」
- 「もうちょっとお友達と一緒にいたかったんだね」
このように、子どもの言葉に共感し、気持ちを言語化して返すことで、「自分の気持ちを伝えていいんだ」という安心感を持つことができます。そのうえで、「でもそろそろ夕飯の時間だから、あと5分で帰ろうね」と、親としての判断を伝えると、子どもも納得しやすくなります。
親が自己主張のモデルになる
子どもは、親の言動をよく見ています。親自身が、自分の気持ちや考えをきちんと伝えているかどうかも、子どもに影響します。
たとえば、
- 「今日はちょっと疲れてるから、静かに過ごしたいな」
- 「私はこう思うけど、あなたはどう思う?」
といった、親自身の感情や考えを丁寧に伝える姿勢は、子どもにとって「自分の気持ちは言っていいんだ」というお手本になります。
また、夫婦間でのやりとりでも、「どうせ分かってくれないから…」と黙ってしまうのではなく、話し合う姿勢を見せることが、子どもの学びになります。
小さな選択肢を与えてみる
「自分で選ぶ」経験も、自己主張を育てる鍵です。
たとえば、朝の服を「どれを着たい?」と選ばせてみる。おやつを「みかんとりんご、どっちがいい?」と選ばせる。こうした小さな選択肢の中で、「自分の意見を言っていい」「自分の考えが尊重される」という感覚を育てることができます。
ただし、どちらを選んでも親が対応できるようにしておくことが大切です。「どれを着てもOK」という前提がないと、「これにしたのに怒られた!」となり、逆効果になることも。
子どもの主張をすべて受け入れる必要はない
親として気をつけたいのは、「自己主張を尊重する=子どもの要求をすべて飲む」ではない、という点です。
たとえば、夜遅くまでゲームをしたいと主張してきた場合、親はその気持ちを一度受け止めたうえで、「でも、明日学校があるから夜更かしはできないよ」と、しっかりと線引きすることが必要です。
「聞いてもらえた」という体験があるだけで、子どもは納得しやすくなります。大事なのは「否定しないで聞く→親の考えを伝える」という順番です。
まとめ:親ができる3つの関わり方
- 子どもの気持ちをまず受け止める →「そう思ったんだね」「そう感じたんだね」と共感する。
- 親自身が気持ちを言葉にする →「私はこう思うよ」と伝える習慣を持つ。
- 小さな選択肢を与えていく →「どっちがいい?」という経験を日常に取り入れる。
子どもが安心して自己主張できる家庭は、信頼関係が育まれ、将来的にも人間関係を築く土台になります。
「ちゃんと自分の思いを伝えられる人になってほしい」
そう願うなら、今からできる親の関わり方を少しずつ実践してみてくださいね。
みなさん!!
子育てを楽しみましょう!!