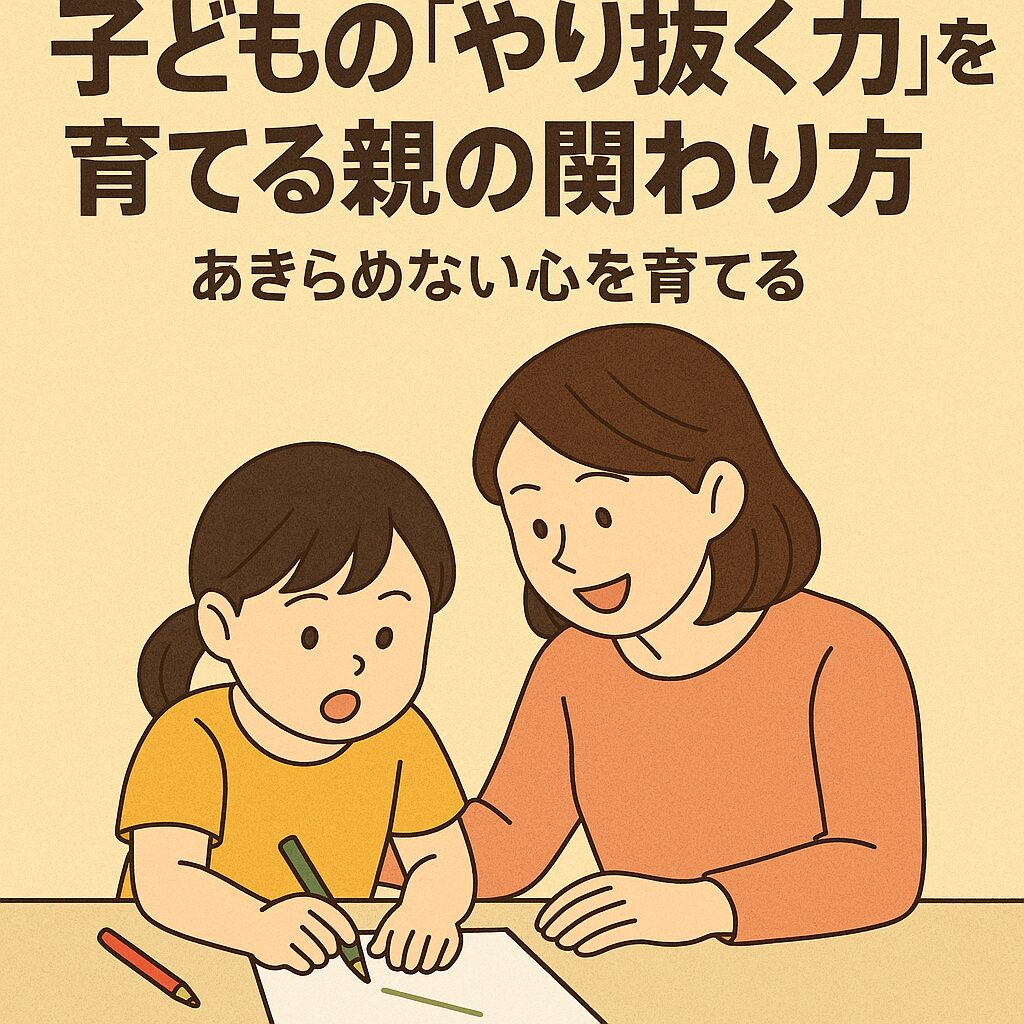〜子どもの「やり抜く力(グリット)」を伸ばす親の関わり方〜
「すぐに飽きちゃう」「やりかけで終わる」「難しいとすぐにやめる」
子どものこんな様子に、心配になったことはありませんか?
現代の教育現場や子育ての中で注目されている力のひとつに「やり抜く力(=グリット:Grit)」があります。これは、IQや才能よりも、人生の成功や満足度に深く関わる力とされ、アメリカの心理学者アンジェラ・ダックワース氏が提唱した概念です。
今回は、この「やり抜く力」を子どもに育むために、親ができる関わり方について具体的に紹介します。
■ 「やり抜く力」とは?
グリットとは、目標に向かって粘り強く努力し続ける力のこと。
ただ「我慢強い」「頑固」ではなく、「情熱」と「粘り強さ」が合わさった力です。
例えば:
- 毎日コツコツ練習して少しずつ上達する
- 失敗しても「次はこうしてみよう」と立ち直る
- 時間がかかっても、目標に向かって努力を続ける
こうした力は、勉強やスポーツだけでなく、人間関係や社会での適応力にも直結します。
■ 子どもが「やり抜けない」原因は?
子どもがすぐに投げ出してしまう背景には、いくつかの要因があります:
- 「うまくできない=失敗」と感じてしまう
- 結果より過程を見てもらえない
- 興味があっても、すぐに否定される
- 成功体験が少なく、自信が育っていない
「飽きっぽい」ように見える子でも、実は「失敗が怖い」だけというケースも少なくありません。
■ グリットを育てる親の声かけ
親の声かけは、子どものやる気や粘り強さに直結します。次のような声かけが効果的です:
- 「がんばってるね」 → 結果より“努力”に注目
- 「失敗しても大丈夫だよ」 → 失敗=成長のチャンスと伝える
- 「どうしたらうまくいくと思う?」 → 自分で考える力を促す
- 「続けていたら少しずつできるようになるよ」 → 成長には時間がかかると理解させる
■ 「挑戦の機会」を意識して作る
子どもが何かに粘り強く取り組むためには、まず「やってみたい」と思える経験が必要です。
たとえば:
- パズルや積み木、ボードゲームなど、達成感を味わえる遊び
- 簡単に終わらないけれど、少し背伸びすればできる課題
- 家のお手伝いや植物の世話など、継続が求められる活動
「できた!」という成功体験を積み重ねることで、「次もがんばってみよう」という気持ちにつながります。
■ 続ける工夫を一緒に考える
子どもが途中で飽きてしまいそうなとき、親が「最後までやりなさい」と叱るのではなく、「どうすれば最後までできそう?」と一緒に工夫する姿勢を持ちましょう。
たとえば:
- タイマーで時間を区切る
- ステップに分けて進める
- 「できたらシール」などのごほうび制
子ども自身が「やり方を選べる」状況をつくることで、自主性も育ちます。
■ 親も「やり抜く姿」を見せる
子どもは親の背中を見て育ちます。
親自身が「苦手だけどがんばってみた」「続けていたら上手くなった」など、自分の体験を言葉で伝えることも、非常に効果的です。
「ママもこの料理、最初はぜんぜん上手に作れなかったけど、何回かやってみたらできるようになったよ」
そんなエピソードが、子どもにとってのヒントになります。
■ おわりに
子どもの「やり抜く力(グリット)」は、短期間で育つものではありません。
毎日の生活の中で、小さな「できた」を積み重ね、失敗してもあきらめずに立ち上がる経験を重ねていくことで、少しずつ育っていきます。
親が見守り、励まし、共に乗り越えることで、子どもは「どんなことでもがんばればできるかもしれない」と思えるようになります。
今日からぜひ、お子さんの「がんばろうとしている姿」に目を向けてみてくださいね。
みなさん!!
子育てを楽しみましょう!!